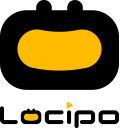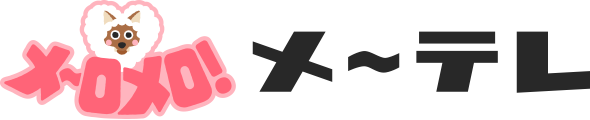TOPIC
放送内容

1972年。日本は電撃的に中国との国交を回復した。きっかけはその一年前、名古屋が舞台となった世界卓球選手権大会であった。中国と日本の新しい関係は、まさに名古屋から始まったのである。
メ~テレは、民放として当時初めて中国国内の取材を許されたテレビ局だった。1971年秋に北京で開かれたジュニア卓球大会、アジア・アフリカ卓球大会を皮切りに、文化大革命真っ只中の北京、日本軍の爪跡が深く残る東北地方、希望に満ちた人民軍など10年間に渡り中国各地を取材し続けた。メ~テレのアーカイブには、今もその貴重なフィルムが残っている。
その中に完成していたのに、32年もの間放送されなかった番組がある。それが、「中国の顔 第13話 ~つぎの世代へ ひき継ぐ者の証言~」である。フィルムには「1976年12月26日放送と記されていた。番組では、「走資派」鄧小平に対する闘争を押し進める重要性を、若者たちが熱く語っていた。
1976年、中国は政治の時代だった。周恩来、毛沢東が相次いで死去。毛沢東の文化大革命を引き継ぐと思われていた「4人組」の逮捕、そして「走資派」として排除されていた鄧小平の復権…。第13話は、中国の政局変化をまともに受けて「幻」となってしまった。中国の政局が変ると放送できなくなる番組とは一体?
あの時熱く政治を語っていた中国の若者たちは今何をしているのか、当時の取材ディレクターは中国取材を振り返って何を思うのか。現代と1970年代の中国の姿を重ねながら「幻の第13話」を検証、当時の中国報道の問題点、そして35年後の今、私たちメディアの果たす役割について考える。

2007年中国北京 天安門

開発の進む北京
スタッフのつぶやき
ディレクター:村瀬 史憲
今回の番組で考えさせられたことは、「偏向報道とはなんぞや」という問いだった。国交正常化前を前にした1972年夏、当社は世界のテレビ局に先駆け中国を単独で取材した。当時の日本政府は台湾の国民党政府を中国の正式な政府とし、中華人民共和国を認めず、佐藤栄作総理も「中共(中国共産党)」と呼んだ。当社の取材は明らかに「一衣帯水の隣国」と言われる中国大陸との関係改善を意図したプロジェクトだった。番組中に登場する社会主義への賛同にも似たナレーション、誇らしげに文革の成果を語る人物が次々と画面に登場することが、その表れだ。
不偏不党を旨とする報道が、イデオロギーを賛美し、「両論」を示さずに行った当時の名古屋テレビの中国報道に、違和感を抱くかもしれない。だが単純に断ずることはできない。1つの国家に対し政府が「中共」という呼称を用いることを容認した当時の日本の世論の中で、「友好的」な中国報道を行うことは相対的には「客観的」だったとも言える。国際的に孤立していた中国が名古屋テレビの姿勢に対し「あなた方は客観的だ」と評価したことも一理ある。
が、しかしだ。提供された情報をそのまま出す、というのは相手がどの国であれ、誰であれ、報道の使命に反すると私は思う。それは政府機関、および公営放送局に任せればよいことで民間放送局がすべきことではない。
安倍前総理の就任直後の訪中で、日中両国は「戦略的互恵関係」の構築を今後、目指すと確認し合った。小難しい名前のこの関係は要するに、単なる「友好、好!」という関係を進化させ、互いのために言うべきことは言い、認めるべきことは認め合うことだという。つまり「遠慮は抜きにして、そろそろ腹を割って話しましょう」ということ。
我々、報道が取るべき姿勢も「友好第一」はもう古い。今後、意義ある中国報道を続けるには、彼の超大国の戦略を抉り出す慧眼と体力が必要だと感じ、深呼吸した。