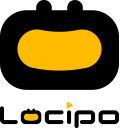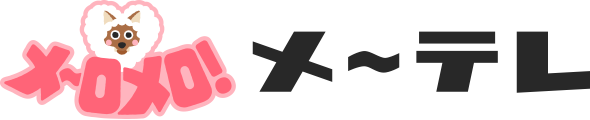TOPIC
放送内容

ハンス・べーテ、フィリップ・モリソン、ルース・アダムス、ジョセフ・ロートブラット。彼らは今年亡くなったマンハッタン計画の科学者たち、しかもそろって戦後「核兵器開発」に反対の姿勢を表明した。なかでもロートブラットは原爆を開発した科学者でありながら戦後「ノーベル平和賞」を受賞した。
そして被爆経験を持つ沢田昭一。名古屋大学名誉教授。広島で被爆した沢田氏の専門は素粒子物理。「僕はひょっとすると日本で、いや世界で唯一の被爆体験のある物理学者かもしれないね」と静かに笑う。被爆者訴訟には証人として、団長として訴訟に関わる。沢田はロートブラットの著書の翻訳者としても知られる。なぜ被爆者が最も憎むマンハッタン計画に関わったロートブラットの本を選んだのか?被爆体験を持つ沢田と原爆開発に関わったロートブラット。この2人は戦後のどの時点でお互いを認め合ったのか?彼らの生き方と長年の交友はどのように築かれたのか?
番組では原爆にかかわった物理学者の戦後を通して「原爆」「科学者」「心の傷」「生き方」をキーワードに「戦後60年」を考える。

ロートブラット

ベーテ夫人
スタッフのつぶやき
ディレクター:土江真樹子
「物理学」「核融合」などという言葉は、私には一生縁がないものだと思っていた。理系に弱い私はアインシュタインの相対性理論など理解できない。そんな私が、物理学者の言葉に耳を傾けたいと思ったのは、原爆を開発した「マンハッタン計画」の中心人物の1人だったハンス・ベーテという物理学者が、クリントン大統領に核兵器開発の中止を要請する手紙を出したというニュースが、あまりにも印象的だったからだ。「米国はすべての核兵器開発からきっぱりと手 を引く時だ」とベーテ博士はクリントン大統領に訴えた。
彼らはどんな人たちなのか?どんな戦後を送ってきたのか?原爆開発に関わった反省から、ベーテは「科学者の責任」ということを戦後、強く訴え続けた。ロートブラットは、今も兵器開発の中心であるアメリカ・ニューメキシコ州のロスアラモス研究所の科学者に「科学者の責任をどうとるのか」と迫った。
今年、マンハッタン計画の科学者4人が亡くなった。その中の2人がベーテとロートブラットだった。2人とも取材のアポが取れていながら間に合わなかった。しかし、彼らが名古屋と強いつながりを持っていたことがわかった。名古屋大学の教授だった沢田昭二さんは、ロートブラットと親交があり、彼の著書の翻訳者でもある。そして、沢田さん自身、広島の被爆者であり、現在も被爆者のための活動を行っている。彼は「被爆者であり物理学者である私の責任」という言葉を講演で何度も口にする。市川芳彦さんはベーテの下で学ぶ学生だった。市川さんは「物理屋としての責任の重さ」ということに何度も直面したと語る。
原爆を開発したという行為、それによって課せられた責任に、どう向き合いつきあっていくか。被爆者であり物理学者である自分は、世界に何を訴える責任を担っているか。私は取材を通して、「科学によって未知の分野を切り拓く者たちの能力と責任」について考えることになった。では、私自身、自分の行為の責任について考えたことがあるだろうか?テレビというメディアに関わる者として、その行為と責任を果たしているだろうか?そんな問かけが取材中、何度も私の脳裏をよぎり、私に答えを迫ってきた。今回の取材は、「責任」という幼い頃から聞きなれた、しかしとても重く困難なことを考える機会となった。