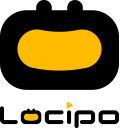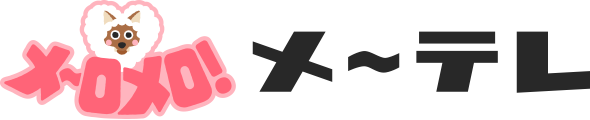TOPIC
放送内容

戦後60年、これまで我々は戦争の悲惨さを伝えてきた。それは「資料」や当事者(体験者)の「記憶」に基づいてのものだった。しかし苛烈な経験をすると、その記憶が「欠落する」ことが最近の研究で分かってきている(PTSD)。今回は戦争により「欠落した記憶」を検証する。地獄絵図となった沖縄戦では語り部の話を聞くと、記憶に空白が多く存在する。また自ら記憶を殺そうと戦後60年間、口を閉ざしている人もいる。沖縄戦に加わった米兵の心にも傷は残っていた。戦後、沖縄戦を振返った元米兵は「血なま臭い事より愉快な出来事のほうをよく覚えている」「こんな不快な事を覚えていて正気でいられるとは思えない」と語っている。これらは最近注目が集まっている「戦争トラウマ(PTSD)」だ。この「戦争トラウマ(PTSD)」はベトナム戦争後に帰還兵に精神障害、「シェルショック」が見られたことから研究が始まった。番組では沖縄戦の体験者のインタビューやカルテ・証言、そして「戦争トラウマ(PTSD)」の研究を始めた名古屋の南山大学生の調査を追い、「戦争が残さなかったもの」「欠落した記憶」を検証する。

南山大学で自らの体験を語る ベトナム退役兵

地獄絵となった沖縄戦
スタッフのつぶやき
ディレクター:土江真樹子
戦後60年、戦争の風化、そして記憶の継承の必要性が強く指摘される。この大きくて重い課題に答えを見出すことはできるのだろうか?
「ヤマトの人には体の中のもんが1つ足りんから」という言葉が返ってきた。これには私はどう反応したらいいのか、さとうきび畑の中でうろたえてしまった。このときの私の質問は「ちむぐりさってどういうことですか?」読谷村では何度も「ちむぐりさ」という言葉を聞いた。戦争体験者が口にするこの言葉の意味やニュアンス掴みかねた。「沖縄では心と頭のほかに肝(ちむ)というもんがあってここがいつまでもじくじくと重苦しく痛む」「だから沖縄戦のことは聞かないで、話したくない、話せないから」と説明を受けたが、取材中、そして今もずっと喉にひっかかった小さな「何か」としてこの言葉が私の気持ちから離れない。わかるようで実感できない。わからないようでいて何か、感じるような。今年の戦後60年の番組企画では「ちむぐりさ」を、そして理解しようと模索する、そんな姿を追いたいと思った。それが戦後60年の「今」ではないか、と考えた。