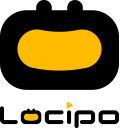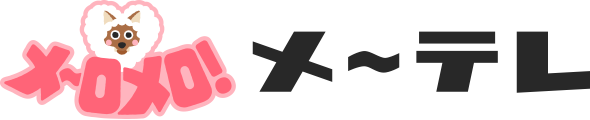TOPIC
放送内容

公共事業のありかたを検証するシリーズ「かたちとゆくえ」第2弾。
日本最大規模のダム・徳山ダムは、あと1年半で巨大なダム本体が完成する。しかし、今年になって、その存在理由が根本から問い直された。450戸余の全村水没・離村という犠牲を払ってつくったダムなのに、その水を必要とするはずの下流の県や市からは、水利権の返上が相次ぐ。唐突な建設費の大幅増という問題も、混乱に拍車をかけた。
余っている水。それなのに、徳山ダムは、建設費を増額してまで作られようとしている。本当に必要なのか?このまま進めばどうなるのか?市民県民の負担増は、いったいいくらになるのか?そのひとつの答えが、運用開始10年となる長良川河口堰だ。河口堰の水はほとんど使われず、逆に建設費の借金返済だけが、住民や自治体を苦しめている。
国と地方の借金が空前のレベルに達する中、徳山ダムは、旧住民の犠牲に値する本当に必要なダムだったのか、厳しく検証する。

市民グループの見学

市民に公団側が説明をする
スタッフのつぶやき
ディレクター:平岩潤
毎月の水道の使用量や料金のお知らせに、目を通したことはありますか?私の場合は、ほとんど無関心でした。ところが、日々のニュースに時々出てくる、徳山ダムの問題を取材してゆくと、この水道料金を通じて、徳山ダムが巨額な無駄を生む、大変な問題であることに気がつきました。私たちは、7月に「かたちとゆくえ 日本一高い!名古屋高速の研究」を放送しましたが、それに続くものとして、この問題を取り上げることにしました。
岐阜県にある、日本最大規模の徳山ダムは、あと3年で完成しますが、知らないうちに、自治体の財政の危機や、水道料金の値上げが近づいています。ダム建設の費用は、本来なら、そこで確保した水を利用者に使ってもらい、その料金収入で返済します。しかし、どこの自治体も「水余り」がひどく、新たに水を確保したからといって、その分を余計に使ってくれる人はいません。結果的に、水道料金を値上げしたり、それでも足らなければ、税金で返すことになります。
徳山ダムの場合は、建設費の大幅増もあり、まさにそうした危機が迫っていますが、「渇水対策」「将来の水源確保」という掛け声の下、実態は住民に知らされないままです。一方で、運用開始10年となる長良川河口堰は、すでに、こうした問題が表面化し、三重県の住民や自治体を苦しめています。番組では、こうした隠された危機の実態を東海3県内で幅広く取材し、暴いてゆきます。
何分、複雑に入り組んだ話で、一部わかりにくい部分もあるかと思いますが、それでも、これだけは言いたいと思います。
徳山ダムは、450戸余の全村水没・離村、そして廃村という犠牲の下に作られました。廃村から17年、かつての村落は、今はダム工事のダンプや重機の行きかう場所でしかありません。徳山ダムはその犠牲に値する、本当に必要なダムだったのか。
この番組を見て、みなさんに考えてもらえればと思います。