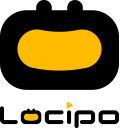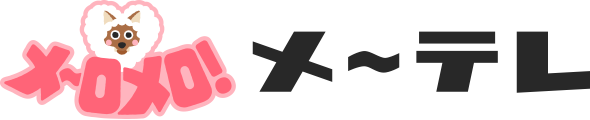TOPIC
放送内容

中国西安からの留学生で、また自ら中国琵琶奏者のティンティンが、自らの音楽の原点を求めて雲南の秘境に旅立つ。雲南の山岳地帯の奥深く、古く美しい町がある。中国の少数民族「納西(ナシ)族」が多く暮らす麗江。標高2400メートルのこの町は1997年、世界遺産に登録された。ここには納西古楽という中国の古い音楽が楽器とともに残され伝えられてきた。中国国内からすでに消え去った漢や元、宋の時代の宮廷音楽が、なぜこの秘境の町に残されたのか。そして文化大革命の嵐を越えて守り抜いた人々の民族の文化に対する思いをティンティンは、音楽家として、そして研究者として探る。
口伝によって伝えられてきた音楽は、今では70歳以上の老演奏家が守り抜くだけである。なぜこの地域にだけ残されたのか不思議だが、山々に閉ざされた秘境ゆえに隔離されてきたという説もある。音楽のほかにも現存する生きた象形文字「東巴(トンバ)文字」が納西族に残されている。
さらに山深く、長江の上流をたどれば、男が妻の家に通う「妻問い婚」の風習を残す納西族の一部<モソ人>の村にも訪ねる。
もはや、現代中国から失われたといわれる古代の音楽や楽器を目にして、ティンティンの興味はもっと素朴に残された音楽との出会いを求めて、さらに長江上流の納西族文化のルーツの村を訪ねた。偶然にもその道は、古代西南シルクロード(茶馬街道…雲南、四川からチベット、ネパールを越えインドにいたる過酷な道)と重なる。
豊かに広がる稲作の田園風景、子供たちに見た日本と同じ遊び、何より、日本人とそっくりな顔を持つ人々、素朴な音楽に漂う懐かしく癒される感覚。ここには遠く離れた日本の原風景に出会ったような錯覚に陥る。古代シルクロードをたどり、日本の奈良正倉院にもたらされた琵琶の原型が、納西古楽の楽器にも見られたのは単なる偶然だろうか。いつのまにか、私たちはアジアの遺伝子を体感する旅となっていった。

納西(ナシ)古楽団

今も秘境とされる雲南

納西(ナシ)族が暮らす麗江の町
スタッフのつぶやき
ディレクター:海老名敏宏
長江(揚子江)上流、金沙江の流れは、雨季の時期と重なって谷底深く茶色の濁流と化していた。険しい山岳地帯を縫うように下る長江は、私の憧れであった。中国雲南省麗江県、少数民族が多く暮らすこの地域は近年になってようやく車が通れる道が開通した。それまでは人々はロバに荷を負わせ険しい山道をたどり、谷をわたりいくつもの峠道を越えなければならなかった。私たちがたどる道も、「茶馬古道」と呼ばれる西南シルクロードのルートである。雲南や四川省の物産をロバに背負わせ、多くの商人たちが遠くチベットやネパールを越え、インドへ向かった世界でもっとも厳しいといわれる道である。秘境であるが故の隔絶された文化が、現在もここに残されてきたのもうなずける。
私が雲南に興味を抱いてきた理由のひとつに、日本文化の源流が雲南にあるという文化人類学者の本を読み漁ってからである。稲作文化の源流、日本人のDNAとよく似た民族構成、日本人とそっくりな顔、その他、日本人の郷愁を誘うような風景にもよく出会った。これらの文化が長江を下り、日本にたどり着いたという想像(空想)は無限のロマンを育ててきた。中国琵琶奏者のティンティン(中部大学大学院博士課程文化人類学専攻)の修士論文を読んで、私の興味はいっそう雲南に惹きつけられた。なにしろ、敦煌の壁画に描かれ、今では失われたといわれた古代楽器や、唐や宋、漢の時代の宮廷音楽が、今もこの地方に暮らす納西族に残されているというのだ。しかも、その古代楽器は、日本の奈良正倉院に伝えられているシルクロードの遺産、古代琵琶にもつながるという。日本の雅楽とつながる音楽が、辺境の山岳地帯に残されている不思議を無視するわけにはいかない。
今回の番組は中国西安からの留学生であり、中国琵琶奏者のティンティンが研究を兼ねて、中国古代の宮廷音楽と楽器のルーツをたどる旅である。