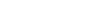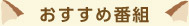五十嵐 信裕
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。
2025/03/09
内閣府が行っている「1日前プロジェクト」は、大災害の被災者の方に「災害の一日前に戻れるとしたら、あなたは何をしますか」と問いかけ、その答えから教訓を考えます。以前も掲載していますが、今回も東日本大震災編から紹介します。 ※肩書き、年齢はアンケート当時のものです。 ※文章・イラストは内閣府の「1日前プロジェクト」HPから。

内閣府の「1日前プロジェクト」HPより
昼食後にコーヒーを飲んでいたら、地震が起きました。すると、目が不自由な主人が「普通の地震じゃないから逃げた方がいい」、「これは大津波の地震だ、いつものと違う、早く逃げろ!」とか言って、階段を降りて行こうとするんですよ。「じゃ、革ジャン着て」って出していたら、「そんなの着ているヒマないよ」って。とにかく着の身着のままで、先に主人を高台の神社に避難させました。
その時、おばあちゃんたちが立っていたので、「大津波が来るみたいだから、早く逃げて!立ってないで!」って言ったら、「そうなの?」って笑っているんです。みんなそんな感じ。「ほんとに来るから!」と叫んでいるところへお店をやっている隣のおばちゃんがリヤカー引っ張って帰ってきたので、「シャッターだけ閉めて逃げて!」と言うと、「だって、今お金を下してきたばっかりだ」って。「いや、とにかく逃げよう」と言って、散乱している店先の物を片づけてやって、シャッターを閉めて、おばちゃんと一緒に逃げました。
実は前の年も大きな地震があって、津波警報が出て、避難命令が出たんだけど、何もなかったんです。それに、あの日の2日前にもちょっとした地震があって、津波注意報が出たけど全然来なかった。そういうこともあったから「たいしたことないな」という気持がどこかにあったのかもしれません。

防潮堤を越えた津波は高い水の壁
防災無線で3メートルぐらいの津波が来ると聞き、アパートの管理人もしていたので、「津波が来るから逃げろ!逃げろ!」と、建物内を言って回って避難させました。ただ、心臓や足腰の悪い人や高齢者、「ここまで来ないから大丈夫だよ」と言っている人たちが12人ぐらい残っていましたので、私も残ることにしました。
1階と2階の人を3階の空き部屋に逃がしてから海の様子を見に行くと、水がダーッと引いて、砂浜に波がチョロチョロときているだけでした。そして、湾の入口の方には、水平線なのか何なのか分からない白い帯がありました。
すると、その白い帯が一気に高くなってきたのです。「3メートルの津波ならたいしたことはない。防潮堤があるから、越えても1メートルぐらいだろう」と思っていたのに、ダーッと波が防潮堤を越えたとたん、立っちゃったんですよ。水の壁みたいに。

根こそぎ流された
津波はまるで大きな川のようになって、畑のビニールハウスやドラム缶、消防ポンプやトラックなどそこにある物すべてをのみこみながら、私たちの目の前をゴーゴーと流れていきました。大木が流されるほどの強い流れでしたからね。近所の娘さんは泳いで何とか助かりましたが、お父さんお母さんは津波の犠牲になりました。
ちょうどその日は、レタスとチンゲン菜の初収穫の日だったのです。うちの奥さんが採った野菜を車に積んで家に帰ったところで、やってきた津波で車は流されました。それから3、4日して、やぶに引っかかっているうちのバンタイプの軽自動車が見つかりました。
車は使いものにならなくなりましたが、野菜を入れていたコンテナは重ねていたので、下の段は泥になっていたけれど、上の段は野菜もきれいでした。で、みんながそれを「野菜がなくなったから」と言ってもらっていきました。うちは野菜中心の食事ですから畑がやられるとどうにもなりません。当時は店にも何もなくて大変でした。
海から3キロも離れているこの地域にまさか津波がくるとは思ってもいませんでした。あれから2年半、震災当時の苦労話をしても、ここから少し離れた駅周辺は全然被災していないから話が合いません。もう風化しつつあるんです。
※「1日前プロジェクト」で検索すると内閣府の1日前プロジェクトのページを見られます。さまざまな災害についての被災者の声が掲載されています。
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。