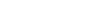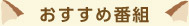五十嵐 信裕
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。
2025/03/16
東日本大震災の時、私は系列応援で仙台の東日本放送と盛岡の岩手朝日テレビでニュース出稿作業を担当した。約3カ月間、被災者・被災地に向き合った。どれも厳しい話題で、映像と原稿を見ていて辛かった。少しでも役に立ちたい。そのためにはどんなニュースを出せばいいのか?毎日、悩んだ。

「笑顔で行ってらっしゃい」「笑顔で行ってきます」
もう一つ悩んだことがある。どうしてこんな事になってしまったのか?東北地方は自治体・住人ともに防災に対する意識が高く、東北局は防災・減災報道に力を入れていた。にもかかわらず多数の死者。同じことが東海地方で起きたらどうなるのか?在名局も防災・減災報道で頑張っているが、まったく不十分ではないのか…名古屋に戻ってからどんな報道をすればいいのか?いまも悩み、考え続けている。
東日本大震災は、私たちにたくさんの教訓を残した。国、自治体など社会への教訓、そして地域、家庭、個人レベルまで、日々の暮らしへの教訓。その中で、私がいまも心がけている教訓がある。それは「笑顔で行ってらっしゃい」だ。
被災地でカメラ取材した映像は、現地に展開している中継車に持ち込まれ、そこから地元局の前線本部に送られてくる。夕方ニュースの締切時間が迫ってくると、取材班が次々と中継車に映像を持ち込む。ある日、前線本部でその映像を見ていてハッとした。

朝の夫婦喧嘩のやりとりが最後の言葉に…
取材を受けている女性は泣いていた。震災当日の朝、ご主人と口論になったそうだ。むしゃくしゃしているうちに、ご主人の出勤時間。顔も見ず声を交わすこともなく会社へ行ったそうだ。
大津波でご主人は帰らぬ人に。朝の夫婦喧嘩のやりとりが最後の言葉になった。
なぜ気持ちよく送り出せなかったのか。いつものように笑顔で「行ってらっしゃい」って言えなかったのか。ケンカの後なので気持ちよくとはいかないが、ひと声かければよかった。あれが最後の言葉になるなんて。口論のきっかけは、ささいなことだったと言う。
同じようなインタビューを、複数の局が放送していた。地元紙でも同じような記事を読んだ。家族での前夜のいさかい、朝のちょっとしたトラブル。それを引きずって出勤、登校。よくある「家庭での朝の一コマ」だ。もちろん我が家でもある。身に覚えがある。
しかし、それが「最後の別れ」になるとは…

後悔をしないように 時間がないときは顔を見るだけでもいい
厳しい状況の中で私たちメディアの取材に応じて下さることは、並大抵の決断ではない。自分の心の傷に触れる話であればなおさらだ。にもかかわらずインタビュー取材に応じてくださった。その思いのすべてはご本人にしかわからない。
しかし、その中に「自分と同じような経験をして欲しくない」という気持ちが入っているのは確かだと思う。
以来、私は、朝は気持ちよく「行ってきます」「行ってらっしゃい」を交わすように心がけている。時間がないときは顔を見るだけでもいい。
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。