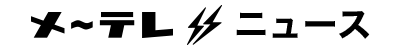熊本地震では震度7が続けて2回 どうすれば!?まずは新耐震基準に【暮らしの防災】
2025年4月13日 14:01
2016年4月14日午後9時26分、熊本県でマグニチュード6.5、最大震度7の地震が発生しました。「熊本地震」です。誰もこれを「本震」と思っていました。(いずれも気象庁マグニチュード=Mj)その28時間後の4月16日午前1時25分、再び熊本でマグニチュード7.3、最大震度7の地震が発生しました。2回目の方が、マグニチュードが大きいので、2回目が「本震」、1回目は「前震」になりました。震度7の地震が同一地域で連続して発生するのは、初めてのことでした。滅多に起きないとは言え、今後、起きないとは言えません。震度7が続けて2回、家は大丈夫なのでしょうか?

熊本地震で動いた断層
震度7が続けて2回
2016年4月14日午後9時26分の地震は日奈久(ひなぐ)断層帯の北端部で発生し、益城町で震度7を観測しました。16日午前1時25分の地震は、そのすぐ北東にある布田川(ふたがわ)断層帯で発生し、益城町と西原村で震度7を観測しました。震度7の地震が同一地域で連続するのは震度7が設定された1949年以降初めてです。
「本震」と思っていた地震の後に、もっとマグニチュードの大きい地震が起きました。「余震」ではなく、こちらが「本震」でした。このため熊本地震以降、気象庁は「地震の今後の見通し」を発表する文の中で「余震」という表現を使わないようになりました。
「余震」というと「最初の地震より規模の小さな地震」という印象を与えてしまいがちです。そこで「最初の大地震と同程度の地震」「規模の大きな地震」という表現で、続いて起きる地震への「警戒」と「備え」を呼びかけているのです。このように「震度7が2回」は、気象庁の発表の表現を変えるほど、地震関係者に衝撃を与えました。
この表現、メディアもしばらくの間は気象庁に合わせていましたが、パッと聞いてわかり難いことなどから、今では「最初の大地震と同程度の余震」という言葉を使っているメディアもあります。いずれにしても、大きな地震の後はしばらく警戒が必要です。

熊本地震で被害にあった住宅(2016年4月)
家は大丈夫? まずは新耐震基準に!
震度7が2回連続すると、建築物へのダメージはかなりのものです。国土交通省住宅局の調査と分析で、次のようになっていました。
■旧耐震基準(1981年5月以前)の木造建築物の倒壊率・・・ 28.2%(214棟)
■新耐震基準(1981年6月~2000年5月)の木造建築物の倒壊率・・・8.7%(76棟)
■2000年基準 (2000年6月以降)・・・2.2%(7棟)
「旧耐震基準の木造建築物の倒壊率は28.2%(214棟)に上っており、新耐震基準の木造建築物の倒壊率と比較して顕著に高かった」としています。新耐震基準、2000年基準の建物は、最初の地震には耐えたとされています。古い家にお住まいの方は、まず耐震改修工事を考えてください。
そして大地震で被災したら避難が必要です。新耐震基準でも2度の震度7はキツそうです。また、被害が大きかった建物の多くは活断層の近くでした。
※出典:平成28年9月12日国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント

耐震等級
新耐震基準をクリアするよう耐震改修工事の検討を
耐震基準とは別の指標・「耐震等級※」で被害を調べると、耐震等級3(倒壊等防止)に該当するものは大きな損傷が見られず、大部分が無被害でした。もちろん住宅を耐震等級3にするには、それなりのコストが必要です。
※建物の耐震性能を表す指標で2000年4月1日に施行。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいた指標です。2024年12月29日掲載の「暮らしの防災」で取り上げています。
ですので、古い住宅に住んでいる場合、まずは新耐震基準をクリアするよう耐震改修工事を検討してください。
<地震で傷んだ家には戻らない>
もう一つ重要な注意点があります。大地震の後、被災者の中に、「何とか揺れに耐えた建物や住宅に貴重品や物資を取りに戻る」方がいます。「避難所はちょっと居心地が悪い」などの理由で、傷んだ家に住み続ける方がいます。これは危険ですので止めましょう。新耐震基準・2000年基準をクリアしている建物でも住み続けることは止めてほしいと考えます。
大地震の場合、最初の地震で建物はかなりのダメージを受けています。見た目で大丈夫でも、あちこちが傷んでいるはずです。そこにまた強い揺れ、激しい揺れが襲ったら、今度は倒壊するかもしれません。せっかく助かったのに2回目の地震で被害を受ける可能性があります。避難してください。大地震の後は建物に入らないようにして下さい。
◇
被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。
■五十嵐 信裕
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。