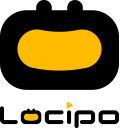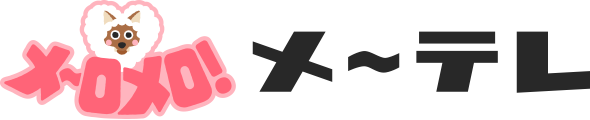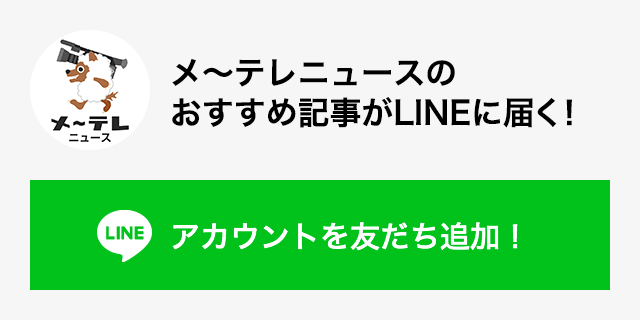洪水の水流を軽減「遊水地」 専門家「注意が必要なのは現場を通行する人たち」
2024年9月2日 19:48
この週末、岐阜県池田町では広い範囲で浸水がありました。原因となったのは、川の氾濫です。その発生地点を見てみると、氾濫が起きやすいとされる、「ある特徴」がありました。
「岐阜県大垣市です。住宅街一帯が冠水してしまっています」(記者)
取材中に、目の前で車がとまってしまうほどの冠水も。
日本列島の広い範囲に記録的大雨をもたらした台風10号。
8月31日、岐阜県池田町では、杭瀬川に流れ込む東川が氾濫。浸水は広い範囲に及びました。
大垣市では一時、赤坂東地区の685世帯に「警戒レベル5」の緊急安全確保が発表されました。
岐阜県によりますと、今回の大雨で大垣市内で住宅2棟が一部破損。
さらに、床上浸水13棟、床下浸水85棟の被害が出ました。
取材中に、目の前で車がとまってしまうほどの冠水も。
日本列島の広い範囲に記録的大雨をもたらした台風10号。
8月31日、岐阜県池田町では、杭瀬川に流れ込む東川が氾濫。浸水は広い範囲に及びました。
大垣市では一時、赤坂東地区の685世帯に「警戒レベル5」の緊急安全確保が発表されました。
岐阜県によりますと、今回の大雨で大垣市内で住宅2棟が一部破損。
さらに、床上浸水13棟、床下浸水85棟の被害が出ました。

浸水被害にあった店の人
「水が来ないと思って、たかをくくっていたら来てしまった」
9月1日、池田町では、グラウンドゴルフ場から流れてきたベンチが水路に詰まり、除去する作業が行われていました。
また、飲食店では――
「川がオーバーフローしてしまったので、それから1時間半くらいでこの高さまで来た。水が来ないと思って、たかをくくっていたら来てしまった」(浸水被害にあった店の人)
客用の座敷が浸水し、畳が濡れてしまい、店の人は、片付け作業に追われました。
今回、氾濫が起きた場所は――
「こちらを流れているのが杭瀬川。そして右手から流れてきた東川と合流するのがこの地点です」(記者)
この場所について、浸水被害があった地域の住民に話を聞くと――
「川が1本あって杭瀬川が通っていて、ちょうどここで合流するが、こっち(杭瀬川)が本線で『バックウォーター』になるので水が戻ってくる。過去にもあったが、ここまでではなかった」(住民)
「そういう地形だから。人間の力で形にできることじゃないから。なかなか難しい」(住民)
また、飲食店では――
「川がオーバーフローしてしまったので、それから1時間半くらいでこの高さまで来た。水が来ないと思って、たかをくくっていたら来てしまった」(浸水被害にあった店の人)
客用の座敷が浸水し、畳が濡れてしまい、店の人は、片付け作業に追われました。
今回、氾濫が起きた場所は――
「こちらを流れているのが杭瀬川。そして右手から流れてきた東川と合流するのがこの地点です」(記者)
この場所について、浸水被害があった地域の住民に話を聞くと――
「川が1本あって杭瀬川が通っていて、ちょうどここで合流するが、こっち(杭瀬川)が本線で『バックウォーター』になるので水が戻ってくる。過去にもあったが、ここまでではなかった」(住民)
「そういう地形だから。人間の力で形にできることじゃないから。なかなか難しい」(住民)

バックウォーター現象
バックウォーター現象とは?
この場所で当時、何が起きていたのでしょうか。
河川工学が専門の名古屋大学・田代喬特任教授に上空からの映像を見てもらいました。
「浸水域の状況を見る限り、いくつかの場所では『バックウォーター』が生じている痕跡が見て取れます」(田代喬 特任教授)
「バックウォーター」とは、大雨などで本流の水位が上昇することで、支流の水がせき止められたり、逆流したりする現象です。
今回は、本流である杭瀬川の水位が上昇したため、支流である東川の水は行き場がなくなり、杭瀬川の濁流も巻き込んで周囲にあふれ出たと田代教授は分析します。
「浸水エリアの中で比較的透明な水と、黄土色・茶色になっている所がある。茶色の水は上流から土砂を運んできた川の水があふれた範囲」(田代 特任教授)
河川工学が専門の名古屋大学・田代喬特任教授に上空からの映像を見てもらいました。
「浸水域の状況を見る限り、いくつかの場所では『バックウォーター』が生じている痕跡が見て取れます」(田代喬 特任教授)
「バックウォーター」とは、大雨などで本流の水位が上昇することで、支流の水がせき止められたり、逆流したりする現象です。
今回は、本流である杭瀬川の水位が上昇したため、支流である東川の水は行き場がなくなり、杭瀬川の濁流も巻き込んで周囲にあふれ出たと田代教授は分析します。
「浸水エリアの中で比較的透明な水と、黄土色・茶色になっている所がある。茶色の水は上流から土砂を運んできた川の水があふれた範囲」(田代 特任教授)

田代喬 特任教授
注意が必要なのは、住んでいる人よりも「現場を通行する人たち」
なぜ、浸水被害は広い範囲に及んだのでしょうか。
現場周辺のハザードマップを確認すると、浸水したエリアは、やや赤みがかった色で示され、周囲と比べて、より浸水しやすい場所だということが分かります。
池田町によりますと、氾濫した東川の堤防は、杭瀬川との合流地点付近で、左岸よりも右岸の方が低く作られているといいます。
「杭瀬川と東川に挟まれた土地。ここは洪水の時に『遊水地』として、洪水の水流を軽減するため、わざとこぼすために作られている土地だと考えられる。想定よりもたくさんの水が流れ込んだこともあったようで、遊水地として考えている区画よりも広い区域で浸水が広がってしまった。住家の一部が水につかってしまったのだろうということが想像されます」(田代 特任教授)
こうした場所では、住宅はすでに「かさ上げ」しているケースがみられますが、注意が必要なのは、住んでいる人よりも「現場を通行する人たち」です。
「その場所に住んでいる人は、ある程度、地域の特性をわかっていると思うが、たまたまその場所に居合わせた人は、リスクを把握するのが難しい。たくさん雨が降ることが想定される、線状降水帯が来るという時は、浸水から避けるという意味では、比較的高い所を選んで通るのは1つの方法かと思います」(田代 特任教授)
現場周辺のハザードマップを確認すると、浸水したエリアは、やや赤みがかった色で示され、周囲と比べて、より浸水しやすい場所だということが分かります。
池田町によりますと、氾濫した東川の堤防は、杭瀬川との合流地点付近で、左岸よりも右岸の方が低く作られているといいます。
「杭瀬川と東川に挟まれた土地。ここは洪水の時に『遊水地』として、洪水の水流を軽減するため、わざとこぼすために作られている土地だと考えられる。想定よりもたくさんの水が流れ込んだこともあったようで、遊水地として考えている区画よりも広い区域で浸水が広がってしまった。住家の一部が水につかってしまったのだろうということが想像されます」(田代 特任教授)
こうした場所では、住宅はすでに「かさ上げ」しているケースがみられますが、注意が必要なのは、住んでいる人よりも「現場を通行する人たち」です。
「その場所に住んでいる人は、ある程度、地域の特性をわかっていると思うが、たまたまその場所に居合わせた人は、リスクを把握するのが難しい。たくさん雨が降ることが想定される、線状降水帯が来るという時は、浸水から避けるという意味では、比較的高い所を選んで通るのは1つの方法かと思います」(田代 特任教授)
これまでに入っているニュース
-
 10歳未満の男の子がはしかに感染 県内で感染が確認されたのは3人目 岐阜県2025年5月11日 19:32
10歳未満の男の子がはしかに感染 県内で感染が確認されたのは3人目 岐阜県2025年5月11日 19:32 -
 鮎の友釣りが解禁 釣り人が長い竿を巧みに操る 三重県大紀町2025年5月11日 19:09
鮎の友釣りが解禁 釣り人が長い竿を巧みに操る 三重県大紀町2025年5月11日 19:09 -
 自宅の包丁で犯行か 祖父殺害容疑で逮捕の少年 愛知・田原市2025年5月11日 18:29
自宅の包丁で犯行か 祖父殺害容疑で逮捕の少年 愛知・田原市2025年5月11日 18:29 -
 「車田」で田植え 岐阜・高山市と新潟・佐渡市のみに残る2025年5月11日 18:29
「車田」で田植え 岐阜・高山市と新潟・佐渡市のみに残る2025年5月11日 18:29 -
 祖父殺害容疑で逮捕の少年 寝室で就寝中に襲ったか 愛知・田原市2025年5月11日 12:32
祖父殺害容疑で逮捕の少年 寝室で就寝中に襲ったか 愛知・田原市2025年5月11日 12:32 -
 80種 2100株のバラの花がみごろ 名古屋・庄内緑地2025年5月11日 12:32
80種 2100株のバラの花がみごろ 名古屋・庄内緑地2025年5月11日 12:32 -
 車中避難(車中泊)への備え 支援物資はすぐに来ない可能性も 小物類を収納ボックスへ【暮らしの防災】2025年5月11日 11:01
車中避難(車中泊)への備え 支援物資はすぐに来ない可能性も 小物類を収納ボックスへ【暮らしの防災】2025年5月11日 11:01 -
 将棋の藤井七冠が名人戦3連勝で防衛に王手2025年5月10日 23:34
将棋の藤井七冠が名人戦3連勝で防衛に王手2025年5月10日 23:34 -
 70代夫婦死亡で遺体に複数の刺し傷や切り傷 孫の少年強い殺意か 愛知県田原市2025年5月10日 22:37
70代夫婦死亡で遺体に複数の刺し傷や切り傷 孫の少年強い殺意か 愛知県田原市2025年5月10日 22:37 -
 車にはねられ5歳の男の子が死亡 三重県明和町 商業施設の駐車場2025年5月10日 22:29
車にはねられ5歳の男の子が死亡 三重県明和町 商業施設の駐車場2025年5月10日 22:29
2
2025-05-10 22:29:02
030065
もっと見る
これまでのニュースを配信中