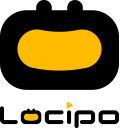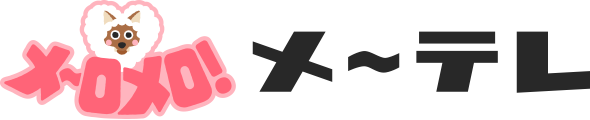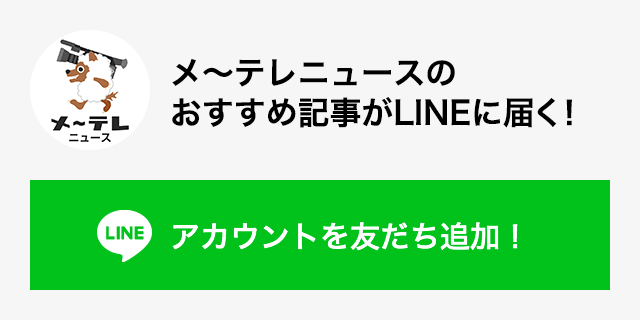子どもの高山病のサイン 推奨標高・年齢は4段階 山で宿泊する場合は「直ぐに寝かせない」
2025年5月10日 08:01
行楽シーズンとなり、登山を親子で楽しもうと考える方も多いかもしれません。登山を計画するにあたり、子どもの年齢に応じて知っておくべきこと、高山病への対策・予防方法や注意点などについて国際山岳医に聞きました。

注意点は4つの段階に分けられる
子どもに推奨される標高と年齢、注意点は4つの段階に分けられる
富士山の診療所で登山者の診療にあたる国際山岳医の大城和恵医師によると、子どもに推奨される標高と年齢、注意点は4つの段階に分けられるといいます。
【新生児及び0歳~2歳未満】
・普通の環境に慣れようとする発育をする時期で、特に低気圧や低酸素に影響されやすいことが指摘されていて、少なくとも生後3カ月までは待つのが良い。
・標高2000メートルを超える場所、宿泊は避けた方が良い。
・急に標高を上げるケーブルカーなどで移動することは避け、徐々に標高に慣れる。
・鼻や耳に何か症状が出ている場合は、圧力のバランスがとれないので登山を控える。
【2歳以上~5歳未満】
・標高3000メートルまで登ることができるが、山小屋などで夜寝る標高は2500メートルまでにする。
・体調が悪くなっても子どもが意思を伝えることが難しいことや、高山病などの症状がわかりにくいので、無理をせずゆっくり標高に順応しながら登り、常に注意を払う。
【5歳以上~10歳未満】
・一般的に3000メートルまで対応出来る。
・体調が悪いことや症状を上手く伝えることが出来る年齢は8歳以上のため、子どもの身体の状態を親が読み取ったり、上手く体調の変化を聞き出しながら、登山に挑戦をする
【10歳以上】
・調子が悪いことを自覚したり、訴えることが出来るようになるので、標高の制限は無くなる。
・初めて高山病になると不安も大きいので、登山前から親子で高山病への理解を深めて症状を疑ったときは親子で冷静に対応出来るようにする。
【新生児及び0歳~2歳未満】
・普通の環境に慣れようとする発育をする時期で、特に低気圧や低酸素に影響されやすいことが指摘されていて、少なくとも生後3カ月までは待つのが良い。
・標高2000メートルを超える場所、宿泊は避けた方が良い。
・急に標高を上げるケーブルカーなどで移動することは避け、徐々に標高に慣れる。
・鼻や耳に何か症状が出ている場合は、圧力のバランスがとれないので登山を控える。
【2歳以上~5歳未満】
・標高3000メートルまで登ることができるが、山小屋などで夜寝る標高は2500メートルまでにする。
・体調が悪くなっても子どもが意思を伝えることが難しいことや、高山病などの症状がわかりにくいので、無理をせずゆっくり標高に順応しながら登り、常に注意を払う。
【5歳以上~10歳未満】
・一般的に3000メートルまで対応出来る。
・体調が悪いことや症状を上手く伝えることが出来る年齢は8歳以上のため、子どもの身体の状態を親が読み取ったり、上手く体調の変化を聞き出しながら、登山に挑戦をする
【10歳以上】
・調子が悪いことを自覚したり、訴えることが出来るようになるので、標高の制限は無くなる。
・初めて高山病になると不安も大きいので、登山前から親子で高山病への理解を深めて症状を疑ったときは親子で冷静に対応出来るようにする。

子どもの高山病の見分け方
子どもの高山病の見分け方
高山病の主な症状として「頭痛」「吐き気」「ふらつき」「不眠」などがありますが、8歳までの子どもやコミュニケーションが苦手な子どもは、症状を説明することが難しい場合があるため、以下の症状があるときは、子どもが高山病のサインを出していると気づくことが大切といいます。
・「ぐずる」
・普段と比べて「元気がない」「食欲がない」「山小屋などで眠れない」
・症状が2つ以上当てはまる場合は、下山することを検討する
<予防策は?>
・高山病は寝ると、呼吸が浅くなって酸素が取り込めなくなり、悪化しやすくなることから、日帰りから始める。
・山で宿泊する場合は、ゆっくりとテント場や山小屋の周辺を歩いたり、座って話したりして、直ぐに寝かせないようにして、高所に慣れる時間をかせぐことが大切だとしています。
・「ぐずる」
・普段と比べて「元気がない」「食欲がない」「山小屋などで眠れない」
・症状が2つ以上当てはまる場合は、下山することを検討する
<予防策は?>
・高山病は寝ると、呼吸が浅くなって酸素が取り込めなくなり、悪化しやすくなることから、日帰りから始める。
・山で宿泊する場合は、ゆっくりとテント場や山小屋の周辺を歩いたり、座って話したりして、直ぐに寝かせないようにして、高所に慣れる時間をかせぐことが大切だとしています。

国際山岳医 大城和恵医師
子どもの気持ちを考えて
富士山の診療所で登山者の診療にあたる大城医師は、診療所に来る子どもに耳を傾けて、そっと話を聴くと「山頂に行きたい」という子もいれば、我慢して親の顔を伺う子、登りたいのか、下りたいのか決められないなど様々な子どもがいるといいます。
診療所に来た子どもに「頭痛い?」と聴くと涙ぐみながら「うん」と答えたところ、親がすかさず「そんなこと言ってなかっただろ」と大きな声をあげる場面もあったといいます。
無理して登頂を果たせば成功体験につながるかもしれないけど、親の前で「登りたくない」「体調が悪い」と本音を言えない子も多いことから、子どもの良い思い出作りになるように、親は冷静になって気持ちに寄り添い、無理なく登山計画を立てて、「安全」と「登山の楽しみ」の両立を図ってほしいと大城医師は訴えます。
診療所に来た子どもに「頭痛い?」と聴くと涙ぐみながら「うん」と答えたところ、親がすかさず「そんなこと言ってなかっただろ」と大きな声をあげる場面もあったといいます。
無理して登頂を果たせば成功体験につながるかもしれないけど、親の前で「登りたくない」「体調が悪い」と本音を言えない子も多いことから、子どもの良い思い出作りになるように、親は冷静になって気持ちに寄り添い、無理なく登山計画を立てて、「安全」と「登山の楽しみ」の両立を図ってほしいと大城医師は訴えます。
これまでに入っているニュース
-
 子どもの高山病のサイン 推奨標高・年齢は4段階 山で宿泊する場合は「直ぐに寝かせない」2025年5月10日 08:01
子どもの高山病のサイン 推奨標高・年齢は4段階 山で宿泊する場合は「直ぐに寝かせない」2025年5月10日 08:01 -
 【速報】愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 孫の16歳の男子高校生を祖父殺害の容疑で逮捕2025年5月10日 06:38
【速報】愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 孫の16歳の男子高校生を祖父殺害の容疑で逮捕2025年5月10日 06:38 -
 岐阜・乗鞍スカイライン 15日の開通を前にシャトルバスが試運転 今も多い所で高さ6メートルの雪の回廊2025年5月10日 00:14
岐阜・乗鞍スカイライン 15日の開通を前にシャトルバスが試運転 今も多い所で高さ6メートルの雪の回廊2025年5月10日 00:14 -
 愛知・田原市の住宅で高齢夫婦死亡 家族が通報「血を流して倒れている」 事件とみて捜査2025年5月10日 00:03
愛知・田原市の住宅で高齢夫婦死亡 家族が通報「血を流して倒れている」 事件とみて捜査2025年5月10日 00:03 -
 対立が続く新アリーナ計画 市民団体が住民投票の実施を求め要望書を提出 愛知県豊橋市2025年5月9日 19:27
対立が続く新アリーナ計画 市民団体が住民投票の実施を求め要望書を提出 愛知県豊橋市2025年5月9日 19:27 -
 藤井聡太七冠が52手目を封じ手にして1日目終了 永瀬拓矢九段が挑戦 名人戦第3局2025年5月9日 19:23
藤井聡太七冠が52手目を封じ手にして1日目終了 永瀬拓矢九段が挑戦 名人戦第3局2025年5月9日 19:23 -
 観光関連事業を巡る贈収賄事件 元担当課長の男、契約の受注企業に口利きか 名古屋2025年5月9日 19:19
観光関連事業を巡る贈収賄事件 元担当課長の男、契約の受注企業に口利きか 名古屋2025年5月9日 19:19 -
 後を絶たない用水路転落事故 下呂市は死亡事故で用水路の一部にふた設置 一方で排水機能低下の懸念も2025年5月9日 19:10
後を絶たない用水路転落事故 下呂市は死亡事故で用水路の一部にふた設置 一方で排水機能低下の懸念も2025年5月9日 19:10 -
 校舎に侵入した不審者への対応を確認 小学校で対応訓練 岐阜2025年5月9日 18:03
校舎に侵入した不審者への対応を確認 小学校で対応訓練 岐阜2025年5月9日 18:03 -
 救急車にあおり運転 男に執行猶予付き判決「執拗に妨害、危険で非常に悪質な犯行」 津地裁2025年5月9日 17:07
救急車にあおり運転 男に執行猶予付き判決「執拗に妨害、危険で非常に悪質な犯行」 津地裁2025年5月9日 17:07
2
2025-05-09 17:07:02
030047
もっと見る
これまでのニュースを配信中