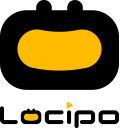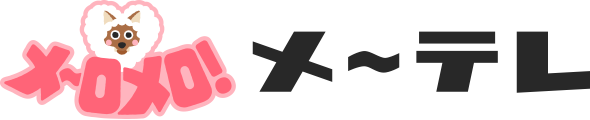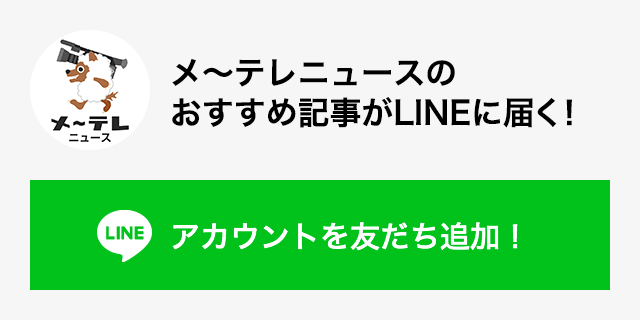大船渡の山火事なぜ長期化 木の内側からあがる炎、土に隠れた熱源を処理する難しさ
2025年3月7日 16:55
岩手県大船渡市の山火事は、いまだに「鎮圧」には至っていません。山火事の消火の難しさについて、名古屋市消防局に話を聞きました。

内側から炎が出ている木を切断する消防隊員(提供:横浜市消防局)
発生から10日が経過し、一時期と比べて火の勢いは弱まりつつある山火事。
一方で警戒が必要なのが、再び発火する恐れがある「熱源」です。
折れた木の内側から炎が上がっています。消防隊員が燃え広がることがないように木を切断しています。
なぜ、木の内側から炎が上がっているのでしょうか。
「木の内側で火災が起きている状況ですね。地表面がすでに焼けている状況がみられますので、地表を伝って火災が延焼したと考えられます」(名古屋市消防局 消防課 大野愛一朗 消防司令補)
また、煙の立ち上る木の根元をシャベルを使って掘り返しています。
「土の中に隠れた熱源や残り火を、効率よく限られた水で消すため、掘りおこしていると思われます」(大野 消防司令補)
一方で警戒が必要なのが、再び発火する恐れがある「熱源」です。
折れた木の内側から炎が上がっています。消防隊員が燃え広がることがないように木を切断しています。
なぜ、木の内側から炎が上がっているのでしょうか。
「木の内側で火災が起きている状況ですね。地表面がすでに焼けている状況がみられますので、地表を伝って火災が延焼したと考えられます」(名古屋市消防局 消防課 大野愛一朗 消防司令補)
また、煙の立ち上る木の根元をシャベルを使って掘り返しています。
「土の中に隠れた熱源や残り火を、効率よく限られた水で消すため、掘りおこしていると思われます」(大野 消防司令補)

山火事の消火の難しさを語る名古屋市消防局の大野愛一朗・消防司令補
「少しの雨だけではなかなか鎮火までは難しい」
「残火(ざんか)」と呼ばれるこうした熱源は現場の至る所に。
現場では雨も降っていますが、それでも不十分だといいます。
「木の内側だったり堆積した落ち葉、落ち枝の下まで水が浸透するというのは難しい状況でしたので、少しの雨だけではなかなか鎮火までは難しいと思われます」(大野 消防司令補)
熱源は、サーモカメラで表面温度を測りながら消火を行い、一定の温度を下回るなどして初めて火が消えたと判断されます。
地中で木の根が燃えている場合もあるため、地面を掘り返して消火する必要もあります。
「なかなかこの残火処理が難しい状況ではあると思うんですけど、この熱源を確認しながら冷却を地道に続けていくしかないと思います」(大野 消防司令補)
避難した住民の疲れもたまる中、残った熱源を重点的に確認しながら消火活動が続きます。
現場では雨も降っていますが、それでも不十分だといいます。
「木の内側だったり堆積した落ち葉、落ち枝の下まで水が浸透するというのは難しい状況でしたので、少しの雨だけではなかなか鎮火までは難しいと思われます」(大野 消防司令補)
熱源は、サーモカメラで表面温度を測りながら消火を行い、一定の温度を下回るなどして初めて火が消えたと判断されます。
地中で木の根が燃えている場合もあるため、地面を掘り返して消火する必要もあります。
「なかなかこの残火処理が難しい状況ではあると思うんですけど、この熱源を確認しながら冷却を地道に続けていくしかないと思います」(大野 消防司令補)
避難した住民の疲れもたまる中、残った熱源を重点的に確認しながら消火活動が続きます。
これまでに入っているニュース
-
 将棋の藤井七冠が名人戦3連勝で防衛に王手2025年5月10日 23:34
将棋の藤井七冠が名人戦3連勝で防衛に王手2025年5月10日 23:34 -
 70代夫婦死亡で遺体に複数の刺し傷や切り傷 孫の少年強い殺意か 愛知県田原市2025年5月10日 22:37
70代夫婦死亡で遺体に複数の刺し傷や切り傷 孫の少年強い殺意か 愛知県田原市2025年5月10日 22:37 -
 車にはねられ5歳の男の子が死亡 三重県明和町 商業施設の駐車場2025年5月10日 22:29
車にはねられ5歳の男の子が死亡 三重県明和町 商業施設の駐車場2025年5月10日 22:29 -
 祖父を殺害容疑で逮捕の少年(16) 第一発見者を装ったか 愛知・田原市2025年5月10日 18:28
祖父を殺害容疑で逮捕の少年(16) 第一発見者を装ったか 愛知・田原市2025年5月10日 18:28 -
 仮眠中の救急隊が指令に気づかず出動遅れ 患者の男性は死亡 名古屋市消防局2025年5月10日 18:28
仮眠中の救急隊が指令に気づかず出動遅れ 患者の男性は死亡 名古屋市消防局2025年5月10日 18:28 -
 中京圏の政財界・文化人の交流の場「ねんげ句会」が設立100周年2025年5月10日 13:13
中京圏の政財界・文化人の交流の場「ねんげ句会」が設立100周年2025年5月10日 13:13 -
 愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 祖父の男性を殺害容疑で孫の16歳少年を逮捕2025年5月10日 13:13
愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 祖父の男性を殺害容疑で孫の16歳少年を逮捕2025年5月10日 13:13 -
 北アルプスの山開き「播隆祭」 登山者の安全を祈願2025年5月10日 13:13
北アルプスの山開き「播隆祭」 登山者の安全を祈願2025年5月10日 13:13 -
 子どもの高山病のサイン 推奨標高・年齢は4段階 山で宿泊する場合は「直ぐに寝かせない」2025年5月10日 08:01
子どもの高山病のサイン 推奨標高・年齢は4段階 山で宿泊する場合は「直ぐに寝かせない」2025年5月10日 08:01 -
 【速報】愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 孫の16歳の男子高校生を祖父殺害の容疑で逮捕2025年5月10日 06:38
【速報】愛知・田原市の住宅に高齢夫婦の遺体 孫の16歳の男子高校生を祖父殺害の容疑で逮捕2025年5月10日 06:38
2
2025-05-10 06:38:01
030057
もっと見る
これまでのニュースを配信中