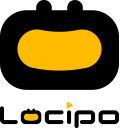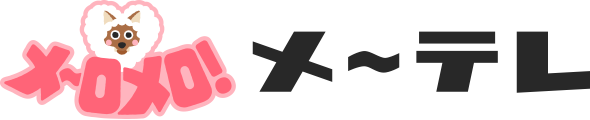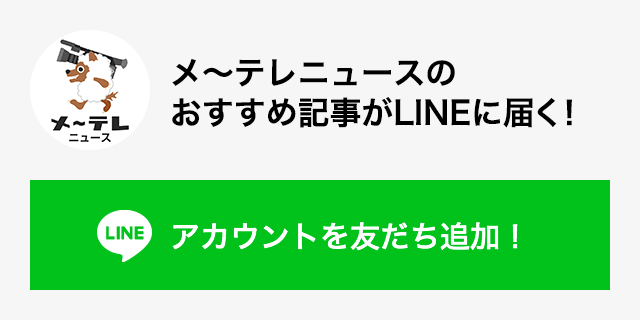ヌルヌル地震で大津波 地震で「弱くゆっくりとした長い揺れ」を感じたら要警戒【暮らしの防災】
2025年3月30日 14:01
東日本大震災について説明する時、「三陸では昔から大地震に伴う津波被害が…」と言います。この「昔の大地震」とは、貞観地震(869年)、慶長三陸地震(1611年)、寛政地震(1793年)、明治三陸地震(1896年)、昭和三陸地震(1933年)などのことです。
このうち「明治三陸地震」では、沿岸での揺れが弱かったにもかかわらず大津波が押し寄せて、約2万2000人が死亡しています。このように規模の割に非常に大きな津波を引き起こす地震を「津波地震」と呼びます。津波から避難するきっかけになる「地震の揺れ」が小さかったため逃げ遅れ、被害が拡大したと言われています。

明治三陸地震の震度分布図「中央気象台(1896)による」出典:地震調査研究推進本部HPより
明治三陸地震
「明治三陸地震」は、発生メカニズムから「ヌルヌル地震」とも呼ばれています。
明治三陸地震は、1896年(明治29年)6月15日午後7時32分頃に発生しました。岩手県釜石市の東200kmの三陸沖が震源です。マグニチュードは、現在では Mw 8.2~8.5 と推定されています。(※気象庁による)
「弱くゆっくりとした長い揺れ」の地震で、震度は2~4と推定され、沿岸部の住民はまさか大津波が来るとは思わなかったと言います。しかし青森県から宮城県にかけての太平洋沿岸を大津波が襲い、最高で約38mの遡上高が記録として残っています。
<ヌルヌル地震>
一般に地震は断層が短時間に一気に割れて「揺れ(地震動)」が生じます。いわば「バキバキ地震」です。一方、津波地震では断層破壊がゆっくりと時間をかけて進みます。これを、その動きのイメージから「ヌルヌル地震」と呼んでいます。「ヌルヌル地震」では、沿岸で地震の強い揺れを感じることはありません。
断層がゆっくりと割れる「ヌルヌル地震」でも、破壊が急速に進む「バキバキ地震」でも、海底で断層が動くということは同じです。ですので、海底で断層破壊がゆっくり進んでも、海底が大きく隆起したり沈降したりすると、その変動が海水に伝わって海面が上下し、津波の発生につながるわけです。
海や河口の近くにいて、地震で「弱くゆっくりとした長い揺れ」を感じたら、要警戒です。
明治三陸地震は、1896年(明治29年)6月15日午後7時32分頃に発生しました。岩手県釜石市の東200kmの三陸沖が震源です。マグニチュードは、現在では Mw 8.2~8.5 と推定されています。(※気象庁による)
「弱くゆっくりとした長い揺れ」の地震で、震度は2~4と推定され、沿岸部の住民はまさか大津波が来るとは思わなかったと言います。しかし青森県から宮城県にかけての太平洋沿岸を大津波が襲い、最高で約38mの遡上高が記録として残っています。
<ヌルヌル地震>
一般に地震は断層が短時間に一気に割れて「揺れ(地震動)」が生じます。いわば「バキバキ地震」です。一方、津波地震では断層破壊がゆっくりと時間をかけて進みます。これを、その動きのイメージから「ヌルヌル地震」と呼んでいます。「ヌルヌル地震」では、沿岸で地震の強い揺れを感じることはありません。
断層がゆっくりと割れる「ヌルヌル地震」でも、破壊が急速に進む「バキバキ地震」でも、海底で断層が動くということは同じです。ですので、海底で断層破壊がゆっくり進んでも、海底が大きく隆起したり沈降したりすると、その変動が海水に伝わって海面が上下し、津波の発生につながるわけです。
海や河口の近くにいて、地震で「弱くゆっくりとした長い揺れ」を感じたら、要警戒です。

S-net 出典:防災科学研究所HP
こまめに情報をチェック
津波地震は揺れが弱いので「あっ!津波が来るかも」と思いつかない可能性があります。明治三陸地震がそうでした。現代の「ヌルヌル地震」対策はどうなっているのでしょう?
□緊急地震速報
震度クラスの揺れの場合、「緊急地震速報(警報=一般向け)」は、発表基準をみたさないので、発表されないと考えられます。しかし、ゆっくりとした大きな揺れ(長周期地震動)が発生するので、「長周期地震動による緊急地震速報」が発表されると思われます。つまり「弱くゆっくりとした長い揺れ」の後に、「緊急地震速報」が出たら津波地震の可能性が高いので“津波に要警戒”、避難です。
□津波警報
防災科学技術研究所の「海底地震・津波観測システム」が、地震のデータをいち早く捉えます。これは海底に地震計や水圧系を設置し、その観測データを光ケーブルで防災科研や気象庁などに送る観測システムです。
日本海溝(S-net)、南海トラフ(DONET1 DONET2 N-net)、相模トラフ(相模湾地震観測施設)があり、24時間太平洋岸の海底を監視しています。この観測データから「津波警報」「大津波警報」がでるはずです。
揺れを感じたら、揺れが大きくても、そう大きくなくても「テレビ」「ラジオ」「スマホ」などで、最新の情報をチェックするようにしてください。
◇
被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。
■五十嵐 信裕
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。
□緊急地震速報
震度クラスの揺れの場合、「緊急地震速報(警報=一般向け)」は、発表基準をみたさないので、発表されないと考えられます。しかし、ゆっくりとした大きな揺れ(長周期地震動)が発生するので、「長周期地震動による緊急地震速報」が発表されると思われます。つまり「弱くゆっくりとした長い揺れ」の後に、「緊急地震速報」が出たら津波地震の可能性が高いので“津波に要警戒”、避難です。
□津波警報
防災科学技術研究所の「海底地震・津波観測システム」が、地震のデータをいち早く捉えます。これは海底に地震計や水圧系を設置し、その観測データを光ケーブルで防災科研や気象庁などに送る観測システムです。
日本海溝(S-net)、南海トラフ(DONET1 DONET2 N-net)、相模トラフ(相模湾地震観測施設)があり、24時間太平洋岸の海底を監視しています。この観測データから「津波警報」「大津波警報」がでるはずです。
揺れを感じたら、揺れが大きくても、そう大きくなくても「テレビ」「ラジオ」「スマホ」などで、最新の情報をチェックするようにしてください。
◇
被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。
■五十嵐 信裕
東京都出身。1990年メ~テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。
これまでに入っているニュース
-
 ビール値上げの影響と対策 酒の専門店「大きな影響ある」 瓶ビール激安の焼き肉店「そのままで」2025年4月2日 19:33
ビール値上げの影響と対策 酒の専門店「大きな影響ある」 瓶ビール激安の焼き肉店「そのままで」2025年4月2日 19:33 -
 投資名目で1350万円だまし取ったとして逮捕された男性を不起訴処分に 津地方検察庁2025年4月2日 17:30
投資名目で1350万円だまし取ったとして逮捕された男性を不起訴処分に 津地方検察庁2025年4月2日 17:30 -
 オンラインゲームが発端、女子高校生の遺体が発見された事件 街で聞いたゲームへの意識2025年4月2日 17:10
オンラインゲームが発端、女子高校生の遺体が発見された事件 街で聞いたゲームへの意識2025年4月2日 17:10 -
 市の中心部で5日に不発弾撤去作業 市バスの運行に影響 1500人が避難対象に 名古屋市2025年4月2日 17:01
市の中心部で5日に不発弾撤去作業 市バスの運行に影響 1500人が避難対象に 名古屋市2025年4月2日 17:01 -
 女子高校生の遺体を遺棄したとして逮捕された男 事件後にDM、生きてるように見せかけか2025年4月2日 16:47
女子高校生の遺体を遺棄したとして逮捕された男 事件後にDM、生きてるように見せかけか2025年4月2日 16:47 -
 標高2156mの展望台で自然感じる入社式 雪が降る中4人に辞令 岐阜県高山市2025年4月2日 12:44
標高2156mの展望台で自然感じる入社式 雪が降る中4人に辞令 岐阜県高山市2025年4月2日 12:44 -
 フグの肝臓を客が持ち帰ったか 県が食べないよう呼びかけ 愛知・蒲郡市の鮮魚店2025年4月2日 12:38
フグの肝臓を客が持ち帰ったか 県が食べないよう呼びかけ 愛知・蒲郡市の鮮魚店2025年4月2日 12:38 -
 【地震】岐阜県美濃中西部を震源とする最大震度1の地震が発生 津波の心配なし2025年4月2日 11:17
【地震】岐阜県美濃中西部を震源とする最大震度1の地震が発生 津波の心配なし2025年4月2日 11:17 -
 女子高校生の遺体が見つかった事件 逮捕された男「女性と口論になって複数回刺した」と供述2025年4月2日 10:44
女子高校生の遺体が見つかった事件 逮捕された男「女性と口論になって複数回刺した」と供述2025年4月2日 10:44 -
 愛知県岡崎市の20代男性がはしかに感染 今年に入り県内で5人目 3月上旬ベトナムに滞在2025年4月1日 22:49
愛知県岡崎市の20代男性がはしかに感染 今年に入り県内で5人目 3月上旬ベトナムに滞在2025年4月1日 22:49
2
2025-04-01 22:49:01
029503
もっと見る
これまでのニュースを配信中